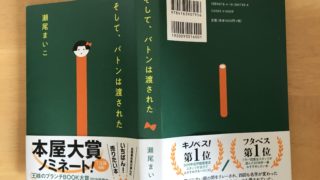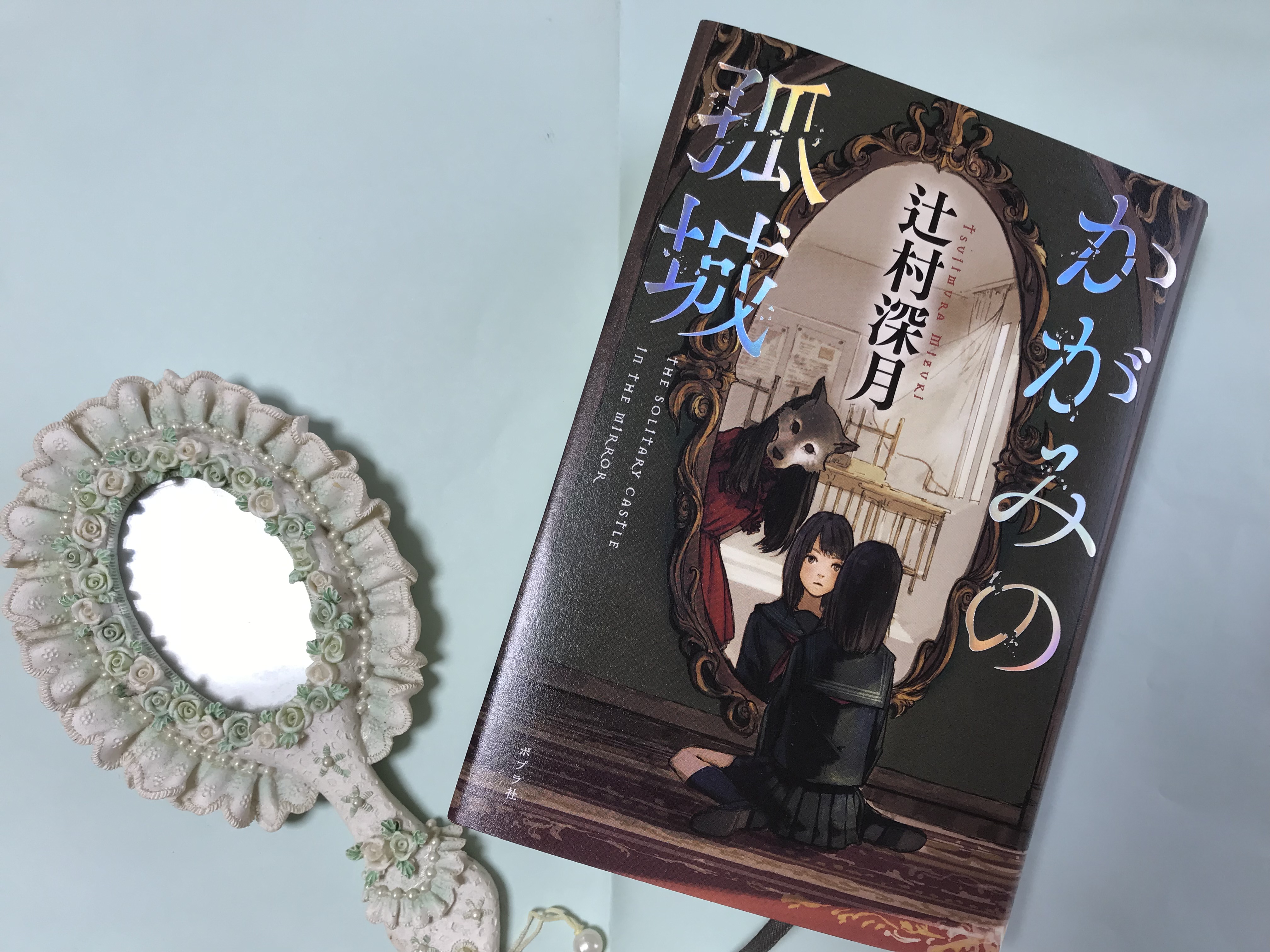皆
さん、NHK大河ドラマ「いだてん」、見てらっしゃいますか?
おもしろいですよねえ。
「マラソンの父」と言われる金栗四三(かなくり しそう)の物語です。
金栗四三は日本人として初めてオリンピックに出場した人であり、箱根駅伝の開催や女子スポーツの普及に大きな貢献をした人です。
大阪のあのグリコの看板のモデルの一人にもなった人なんですよ。
金栗四三は熊本出身なので、今、私の住んでいる熊本では「いだてん」で盛り上がっています。
熊本空港にはこんなパネルがあるくらいです 😀 
今回は、この金栗四三の生い立ちと家族、子孫そして残した名言についてお伝えしていきます。
それから最近、金栗四三の貴重な全身写真が発見されたそうですよ。
そのことについてもお伝えしますね。
金栗四三の妻と子供についてはこちらをご覧ください。
また、金栗四三の生誕の地、熊本県和水町に金栗四三ミュージアムができました!
詳しくはこちらの記事をご覧ください。

金栗四三生家記念館についてはこちらをどうぞ。

玉名市にできたいだてん大河ドラマ館についてはこちらをどうぞ。

金栗四三の生い立ち
 金栗四三は1891(明治24)年8月20日、 熊本県玉名郡春富村(今の和水町)に生まれました。
金栗四三は1891(明治24)年8月20日、 熊本県玉名郡春富村(今の和水町)に生まれました。
金栗四三の生家は酒造業を営んでいて、四三は8人兄姉の7番目として生まれました。
「四三」という名前は、四三が生まれた時、父親が43歳だったからという理由で付けられたそうです。
金栗四三は小さい頃は虚弱体質だったそうです。
でも小学校に入る頃には元気な少年になり、地元の吉地尋常小学校に入学します。
そして10歳で玉名北高等小学校に入学すると、往復12㎞の距離を、毎日、上級生や友達と走って通学したそうです。
四三はこの頃、2回吸って2回吐くという呼吸で走ると苦しくないということに気づきます。
この経験が後の金栗四三を作り上げる大きな力となります。
その後海軍兵学校を目指すのですが、過去に患った結膜炎のせいで不合格になり、次は中国に渡って大成することを夢見ます。
しかし兄に諭され、受験の練習のために受けた東京高等師範学校(今の筑波大学)に進学することになります。1910(明治43)年のことです。
入学した東京高等師範学校で開かれた長距離走大会で3位になり、校長先生に大変褒められたそうです。その校長先生というのは講道館柔道の創始者である嘉納治五郎だったのです。
この出会いが金栗四三の運命を大きく決定づけることになります。
1911(明治44)年、金栗四三は東京高等師範学校の本科に進み、徒歩部に入ります。
人の2倍練習を続けた四三は徒歩部で一番の長距離ランナーになりました。
ちょうどその年、日本のオリンピック初参加に向けた国内予選会が開かれることになり、四三も参加することにしました。
当日は悪天候で、とても寒い日でしたが、四三は黒足袋でがんばり、みごと優勝することができました。
何と当時の世界記録を27分も縮める2時間32分45秒というすごい結果でした。
そして1912(明治45)年、いよいよ日本が初参加する第5回オリンピック ストックホルム大会がやってきました。
マラソン競技の当日は大変な猛暑で、選手68人中34人が棄権するという状況でした。
四三も途中で熱中症になり、意識がもうろうとなって走れなくなり、近くのペトレ家で介抱されることになります。
四三が目を覚ました時は何と翌日になっていたそうです。
大会会場に戻って来なかった金栗四三は「消えた日本人」として噂になったのだそうです。

1914(大正3)年、金栗四三は東京高等師範を卒業し研究科へ進みます。
その年、池部家の養子となり、4月に春野スヤさんと結婚。四三が22歳の時です。
その後は東京府女子師範学校などで教壇に立ちながら、後進の指導にも力を注ぎます。
四三はストックホルム大会での雪辱を晴らすために、第6回ベルリン大会に向けてがんばるのですが、悔しいことに第一次世界大戦のために中止となります。
それから4年後、第7回アントワープ大会に出場するのですが、メダルには届かず16位という結果でした。
33歳の時、第8回パリ大会にも出場しますが、途中で意識不明となり棄権をすることになります。
1945(昭和20)年、熊本に帰郷すると、熊本県体育協会の設立に力を注ぎ、翌年初代会長に就任します。
1948年には熊本県の初代教育委員長に就任。
その後、紫綬褒章、勲四等旭日小綬章を受章。
1967年、75歳の時、スウェーデンオリンピック委員会から第5回オリンピックの55周年記念祝賀行事に招待されました。
金栗四三は大観衆が見守る中、ストックホルムスタジアムを10m程走り、用意されていたゴールテープを切ったのです。
この時、次のような場内アナウンスが流れました。
日本の金栗選手、ただ今ゴールイン。記録は通算54年と8月6日5時間32分20秒3。これをもちまして第5回ストックホルムオリンピック大会の全日程を終了といたします
引用元 http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/112/2193.html
何とも感動的なお話ですね。
そして1983年11月13日、92歳で永眠します。
家族について

それでは金栗四三の家族についてまとめておきます。
金栗四三の父は信彦で、造り酒屋を営んでいましたが、体が弱かったので、43歳で四三が誕生した時には引退していたそうです。
母はシエ。
4人の男子と4人の女子を儲けます。
四三は幼い頃、虚弱体質だったので、四三が東京高等師範学校での長距離走大会で3位になったと知らせた時も、とても心配したのだそうです。
それで、それ以来は陸上でいい成績を収めても、実家にはあまり知らせないようにしたということです。
実次(さねつぐ)、又作(またさく)という名の兄がいます。他の兄弟姉妹の名前は分かりませんでした。
父親が早くに亡くなったので、兄の実次が父親代わりとなって四三を育てました。
夫に先立たれた池辺という親戚の女性が、四三を養子にしたいと頼んだので、四三は池辺家の養子になりますが、養子先の配慮で、姓は金栗で通しました。
結婚した妻の名前は春野スヤと言い、熊本県玉名郡石貫村(現在の玉名市)にある医院の娘でした。
二人には6人の子どもが授かりました。孫は10人できました。
子孫は?
6人の子供と10人の孫に恵まれた金栗四三。
ひ孫も何人もおられるでしょうけれど、そのうちの一人に蔵土義明さんがおられます。
蔵土義明さんは、2012年7月に、ストックホルム大会開催100週年式典に招かれ、四三と同じ「822番」のゼッケンをつけ、四三と同じマラソンコースを完走しました。
また当時の玉名市長とともに、金栗四三の功績をたたえた顕彰銘板の除幕式に参加しました。
そして、四三を介抱したペトレ家を訪ね、お礼をしたそうです。
蔵土義明さんはマラソンの後、こう語っておられます。
走っている途中多くの方から「日本がんばれ」と声をかけていただき、スウェーデンの方の温かさ、曽祖父の偉大さを感じました
名言も紹介!
金栗四三は日本のマラソン界やスポーツ界に偉大な功績を残した人ですが、とてもユーモアに溢れた人でもあったようです。
そんな金栗四三の名言がいくつか残されていますが、ここではその中の3つを紹介しようと思います。
体力、気力、努力
金栗四三の残した有名な言葉です。
金栗四三が歩んできた道そのものですね。
玉名市上小田のお墓と同じ場所に建てられた記念碑にはこの文字が彫ってあります。
長い道のりでした。その間に妻をめとり、子ども6人と孫10人ができました
私は、オリンピックで、ついに優勝ばできんかったとじゃ。ばってん、あの第5回ストックホルムの大会に出場したオリンピック選手は、みな、亡くなってわし一人になったとじゃ、長生き競争には、わしが一番たい。はっはは
92歳で入院した時、お見舞いに来た教え子達に向けて言った言葉です。
金栗四三の写真について
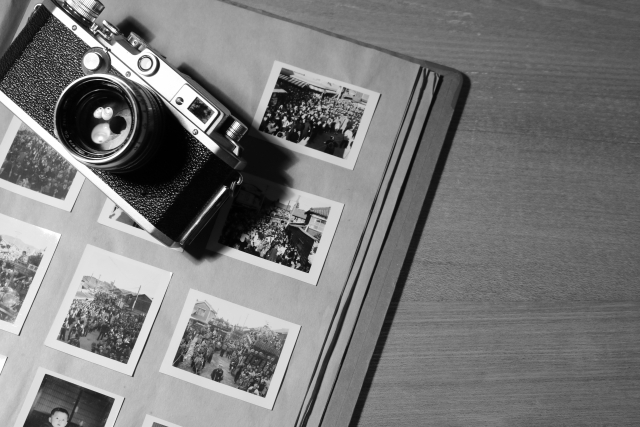
今年の3月に金栗四三の全身写真が発見されたそうです。
今までは上半身の写真がよく知られていたのですが、今度見つかった写真は頭のてっぺんから足先まで映っていて、マラソン用の足袋を履いています。
二の丸の旗の前にユニホーム姿で直立している金栗四三の胸には日の丸と「822」のゼッケンがついているので、ストックホルム大会から帰国した1912年10月のものだと分かります。
表情はとても真面目で素朴な感じです。
足は筋肉が盛り上がっていて、足首はキュッと細く、無駄なところは全くありません。
金栗四三が長年走り続けて、体を鍛えてきたことがよく分かる写真です。
とても貴重な一枚が見つかってよかったです。
押し花と妻への手紙
 acworksさんによる写真ACからの写真
acworksさんによる写真ACからの写真
金栗四三が亡くなって17年後の2000年に、遺族が生まれ故郷の三加和町(今の和水町)と後に過ごした玉名市に金栗四三の遺品をたくさん寄贈しました。
寄贈された本の中からいくつもの押し花が見つかったそうです。
それは、ストックホルムから持ち帰ったものでした。
初めてのオリンピックに臨んだストックホルムで、厳しい練習の合間に花を摘む優しい金栗四三の姿が想像されます。
また、アントワープ大会から帰る途中に妻スヤさんに宛てた手紙も玉名市には残っています。
そこには、第1次世界大戦の傷跡が残る都市の様子が書いてあり、最後は「戦は惨めなものだ。」と結ばれています。
また金栗四三は、オリンピックに出場するために、マラソンだけでなく英語やドイツ語、フランス語の勉強にも力を入れていたことが、遺品から分かります。
まとめ
金栗四三のマラソンにかけた生涯はいかがでしたか?
こんな人が私の故郷、熊本におられたことをとても誇りに思います。
「いだてん」、まだまだおもしろくなりますよ。
楽しみです。
最後まで読んでくださってありがとうございました。