今村翔吾さんの「塞王の楯」が第166回直木賞を受賞しました!
私は読み始めるのが遅くて、「塞王の楯」を読んでいる途中で直木賞発表になってしまいました。
私は歴史ものが苦手なんですけど、今村翔吾さんの小説は読んでいるうちに映像が浮かび上がり、登場人物の心がとてもよく分かります。
「塞王の楯」は、今村翔吾さんの他の作品と同じように民衆の視点で書かれていて、子供へのまなざしが温かく、戦いのない平和な世の中を作るにはどうしたらいいのかという問いが始めから終わりまで流れています。
今回は、第166回直木賞に輝いた、今村翔吾さんの「塞王の楯」のあらすじと考察、書評、そして私の感想もお伝えします。
著者、今村翔吾さんについては、こちらをご覧ください。

第163回直木賞候補作「じんかん」についてはこちらをどうぞ。

「塞王の楯」のあらすじと内容
 主人公、飛田匡介(とびた きょうすけ)
主人公、飛田匡介(とびた きょうすけ)
は子供の頃、故郷、一乗谷の落城により、両親と妹を亡くしました。
匡介は必死で逃げる途中で、石垣職人の源斎(げんさい)に拾われ、育てられます。
源斎は石垣職人の集団である穴太衆(あのうしゅう)、飛田屋の頭でした。
やがて匡介は才覚を現し、源斎の後を継いで、飛田屋の頭となります。
匡介は大人になっても、戦の中で死んでいった幼い妹の泣き叫ぶ顔を忘れることはできませんでした。
そして、絶対に落とされない最強の石垣を作ることが、戦のない世の中を作ることになると信じ、ひたすら石積みの修行を重ね、技を磨いて来ました。
その匡介に対抗するのが、鉄砲職人の国友彦九郎(げんくろう)です。
彦九郎は最強の鉄砲を作れば、それが抑止力となり、戦いを終わらせることができると信じていました。
豊臣秀吉が天下を取り、世の中はしばらく平和でしたが、秀吉が病死すると、その平和が揺らいできました。
大津城主、京極高次(きょうごくたかつぐ)は匡介に石垣の改修を依頼します。
そして敵方の石田三成は、彦九郎に鉄砲作りを依頼しました。
こうして、最強の盾と最強の矛の戦いが始まるのです。
「塞王の楯」の考察

以下は「塞王の楯」についての考察です。
「塞王の楯」の意味は?
穴太衆が信仰しているのは「塞の神」という石造りの神でした。
塞の神は、石によって村を災害から守ってくれるのですが、「賽」という三途の川の河原を守る神とも思われていました。
賽の河原では、親よりも早く死んだ子供が石を積み、それが完成すると成仏できるのですが、完成間際に鬼がその塔を壊してしまう。
でも諦めずに積み続けると救われると信じられていました。
これを聞いた匡介は、死んだ妹のことを思い、よく河原で石積みをしました。
「塞王」というのは、塞の神の加護のもとで最高の石造りの技を持つ者のことで、飛田源斎が「塞王」と呼ばれていました。
時が経ち、大津城での激しい攻防戦の最中、匡介は弾丸からある母子を守った際に命の危機に瀕し、意識がなくなります。
その中で、死んだ妹が賽の河原で石積みをしている夢を見るのです。
何度崩されても、妹はまた石を積んでいきます。
そこで、あることに気が付いた。花代の目は絶望に染まってはいない。しっかりと前を見据え、歯を食い縛り、石をまた積み上げていく。(中略)
また1つ、石を積み上げた時、花代は微かに口を綻ばせて言った。「諦めないで」
この言葉がその後の匡介の確かな力となります。
源斎は奥義は「技」ではないと言っていた。言葉で伝えても意味がないとも、そしてすでに伝えているとも。一つだと何の変哲もない石も、寄せ合い、噛み合って強固な石垣になる。人もまた同じではないか。
果たして「塞王の盾」の正体とは?
匡介と彦九郎の共通点と相違点
匡介も彦九郎も両親を失い、義父に育てられ、義父を超えるような立派な跡継ぎになるという共通点があります。
そして、匡介はどんな攻めも守り抜く最強の盾、石垣を、彦九郎はどんな城でも打ち抜く至高の矛、鉄砲を作るのです。
そんな二人には戦いのない泰平の世を作りたいという願いがありました。
しかし、彦九郎は大量に人を殺す恐ろしい銃を作ることで戦をなくすと言うのでした。
泰平の世を作るために必要なのは何か?
彦九郎の論理は、現在にも生きています。
アメリカなどの銃社会は、身を守るために銃を持つということです。
そして、核保有もそうです。
攻められないために恐ろしい破壊力を持つ核兵器を保有する。
果たして、戦争のない世界を作るために必要なのは何なのか?
今村翔吾さんは、この作品を通して、その問いを投げかけています。
人の強さとは?
大津城主の京極高次は世間から「蛍大名」というあだ名で呼ばれていました。
それは功績を上げることもできず、危ない時は身を守るために逃げ、実力ではなく身内の力で出世したという軽蔑の意味を含んでいました。
しかし、匡介が実際に会った高次は、確かに抜けてはいますが、民衆を差別せず、誰をも大事にし、皆に愛される城主でした。
その高次がいたから、激しい攻防の時も大津城は大名から民衆まで皆が心一つになることができたのです。
本当の強さとは、表面的に人を威嚇するようなものではなく、高次が持っているようなものではないでしょうか。
そして最後に、高次が大音量での一言を発し、戦いを終わらせるのです。
ここに本当の人の強さがあるのではないでしょうか。
夏帆との行方は?
京極高次の妻であるお初の侍女、夏帆は子供の頃に落城を二度も経験し、一度目の落城で両親を失いました。
匡介と夏帆は大津城の改修の時に出会い、互いに惹かれていきます。
最終的にこの二人はどうなるのか・・・・最後まで読んでくださいね。
「塞王の楯」の書評を紹介

それでは、お二人の方の「塞王の盾」についての書評を紹介します。
(前略)
では何故、今村翔吾はかくも苛烈なる戦国小説を世に問うのか。
ここで思い起こしていただきたいのが、先に少し引用した匡介と玲次の会話である。匡介は玲次の「その(命を守った)先、何を守るものがある」の答えとして「泰平を」といっているのだ。
『戦争と平和』を書いたトルストイの昔から、優れた一団の作家たちは、祈りにも似た思いで、〝世の中から戦争をなくすために〟作品を書いてきた。
決して大げさではない。
〝穴太衆〟と〝国友衆〟―究極の二集団を描いた本書には、正にそうした思いがこめられてはいないだろうか。私にはそう思えてならないのである。
(縄田一男さんによる書評)
引用元
(前略)
だがその興奮と裏腹に、読み進むにつれて次第に胸が締め付けられる。匡介も彦九郎も目指すのは戦を終わらせることなのに、自分が組んだ石垣で、自分の作った鉄砲で、人が死んでゆく。自分たちこそが戦火を大きくしているという事実。矛も楯も、己の中に抱える矛楯(むじゅん)に苛(さいな)まれるのである。
その矛楯の行き着く果てはどこなのか。答えが出たとき、物語のすべてが最初からそこに向けて構成されていたことに気づき、溜息(ためいき)が漏れた。石垣のように緻密(ちみつ)に組まれ、石垣のように強固な要を持つ物語である。その石垣の隙間から染み出す熱が読者を搦(から)めとる。
戦国の技術立国・近江を舞台に職人の技術と信念を描いた、読み応え満点の歴史小説だ。お見事。(大矢博子さんによる書評)
引用元 https://book.asahi.com/article/14489531
「塞王の楯」を読んだ感想
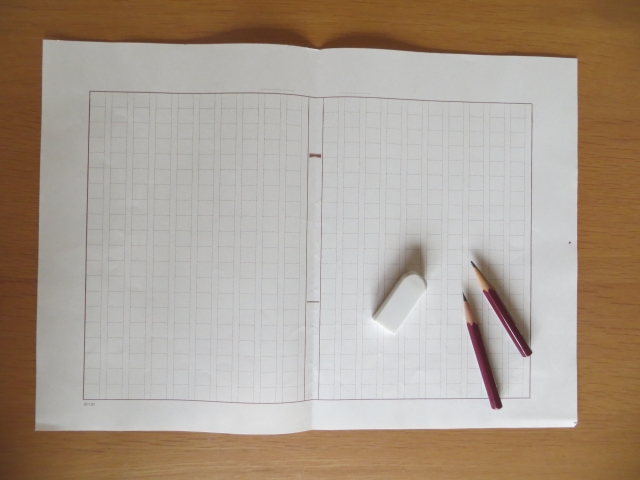
最後に、「塞王の盾」を読んだ私の感想もお伝えします。
まず、石垣を造るという仕事の綿密さ、奥深さに驚きました。
私の故郷、熊本には加藤清正が築城した熊本城があります。
熊本城には「武者返し」と呼ばれる石垣があり、その立派な姿は熊本県人の誇りともなっています。
「塞王の盾」には、石垣を造る職人達の技と誇り、そして戦のない世にしたいという願いが細やかに表されていました。
「熊本城も、こんな風に石が積まれていったのだなあ。」と感慨深い気持ちになりました。
そして、この物語には武士もたくさん登場するのですが、主人公が石積みの職人というところも、今村翔吾さんらしいと思いました。
また「じんかん」もそうでしたが、最初に出てくるのは子供で、今村翔吾さんの子供に対する温かい視線を感じます。
さて、戦のない世の中にするにはどうしたらいいのかという大きな問いが、この物語にずっと流れています。
これは時が流れ、現代になっても人間が解決することのできない問題です。
「平和を守る」と言いながら、空爆によって民衆が殺される、そんなことも思い出されました。
また、物語の最後の方の、大筒で撃たれても撃たれても石を積み直す飛田屋の職人達の姿を見ながら、昔観た映画「ガンジー」のワンシーンが浮かんで来ました。
石積みの職人達の姿が、倒されても倒されても無暴力で進んでいく民衆の姿と重なり、熱いものが込み上げました。
匡介の夢の中で、死んだ妹が何千回、何万回と石を積み、「諦めないで」と匡介に言う場面がここにつながります。
そして、石を積むということが、力のない一人ひとりが集まり噛み合って大きな力を生み出す人の世界と同じだと教えてくれました。
鉄砲職人の彦九郎も本気で戦のない平和な世の中を作りたいと願って銃を作り、そして心の中で矛盾も感じていました。
私達も、争いのない世界を作るためには何ができるのか、一人ひとりが考えていかなければいけないのだと、「塞王の盾」から教えられました。





















